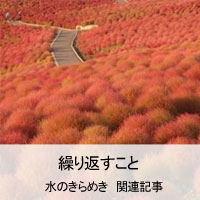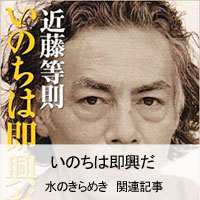須原一秀という哲学者の本。「自死という生き方〜覚悟して逝った哲学者」を読んだ。
「おくりびと」がアカデミー賞外国語映画賞を取り、死について考える人が多くなってきているんだろうなと思う。去年僕も見て感動した。何度も泣かされました、いろんなシーンで。しかし「おくりびと」はあくまでも他者の死である。つまり自分以外の死を扱うことだ。ところがこの本、他の「死」を考えた本と徹底的に違うのは「自分の死について」の本なのだ。
「自分の死なんて、死んだことがないんだからわかるわけないじゃん」と思うかもしれないが、この本は著者自身が最後に死ぬよと予言して、きちんと死ぬのである。だから著者のあとがきのあとに、家族からとしてご子息がコメントしている。
一言で言うと父は毎日楽しそうな人でした。
お酒を飲むこと、銭湯に行くこと、運動をすることが好きで、友人も多く、還暦を過ぎても変わらずエネルギッシュに、若い自分よりよほど人生を楽しんでいるように見えました。
その父が、突然自死を遂げたと聞いた時、もちろんとても驚きました。
文字通り腰が抜けてしまいそうになるほどの衝撃でしたが、その反面、「父らしい最期だったな」と妙に納得させられた面もありました。
とは言え、父には借金や病気、その他一般的な自殺をする理由がなかったことは、一番側にいた母を含め、家族として断言できます。
父らしい、と思ったのは、以前から母に「死ぬときは潔く死ぬ」といった内容の事を話していたのを私も聞いていたからです。
そのせいか、どこかで心の準備が出来ていたのだと思います。
「自死という生き方〜覚悟して逝った哲学者」 須原一秀著 双葉社刊
「最後に 家族から」 抜粋
この本は「自殺」についての本ではない。「自死」についての本だ。「自殺」と「自死」では何が違うかというと、「自殺」は現在の状況からの逃避として死ぬ、「自死」は逃避ではなく、自主的に死を選択して死ぬことだ。だから須原氏は人生に苦しんだり、嫌気がさして死んだのではない。「楽しい人生をまっとうするため」に死を選んだのだ。その考え方を多くの人に理解してもらうために「新葉隠〜死の積極的受容と消極的受容」という本を書いた。それをこの本の編集者が浅羽通明氏の解説と、さきほど抜粋したご子息からの文章を加えて「自死という生き方〜覚悟して逝った哲学者」という本にした。
実は僕も同じ事を考えたことがある。それは小説のプロットを考えていたときだった。次第に医療が発達し、お金持ちは十二分な医療を受けられるようになったため、いつまでも生きていようという「選択」ができる。しかし、生物はいつか死ぬものだ。なので積極的に死を選ぶと言うことがあっても不思議ではないと思ったのだ。自分で立てなくなり、思うように動けなくなったとき、果たしてどうするか。このからだを脱いで、次の生へと旅立とうとするのではないかと考えたのだ。輪廻転生が実際にあるかどうかはわからないが、もしそのことを信じていると、自分からの脱皮はさらに容易にできるようになるなと考えた。
しかし、僕の場合は考えただけである。
須原氏はそのことを考え抜き、プロジェクトのようにして死に至る。その死までの考えを一冊にまとめたのだ。
この本の中で特にすごいと思ったのは「死の能動的ないし積極的受容の五段階」というものを理論として書いているところだ。キューブラーロスの「死の受容に関する五段階説」を参考に考えたそうだが、ひとつひとつ丁寧に考えていくと、自分も死に引きずり込まれそうだ。以下に引用するが、自分は引きずり込まれないという自信のある人が読んでください。
1「人生の高」と「自分自身の高」についておおよその納得
a 楽しいこと、うれしいこと、感激すること、苦しいこと、悲しいこと、などの
経験を通して、結局「人間が生まれて成長し、良いことも悪いこともあって、
老化して死んでいく」という人生全体についてのおおよそを体で納得していることb 自分にできることの範囲のおおよその見当と、自分のして来たこと全体に対する
おおよその見通しを体で納得していることc 種々の「極み」を達成することによって、「自分は確かに生きた」という思いを
日々体で納得していること2死についての体感としての知識
a 自然死・事故死・老化・病気についての経験と学習と熟考
b 日ごろからの人生と死についての経験と学習と熟考
c その結果、「自分の死」(一人称の死)と「縁者の死」(二人称の死)と「他人の死」
(三人称の死)の違いを、実感かつ体感として区別し、理解できること3「自分の死」に対しての主体性の確立
a 「自然死」に対しての主体性の確立(「自然死」の意義を自ら確認し、一人称の
立場で「どんな悲惨な形であってもかまわない。耐えて死んでみせる」という
覚悟と共に、「自然死」を自ら選択し、ゆるがないこと)b 「人工死」に対しての主体性の確立(「病気・老化・死」という一連の運命に
受動的に流されることを拒否するための方策として、「意思的自死」の意義を
確認し、一人称の立場で葉隠的「死に狂い」の心構えを構築すること)4キッカケ待ちとその意味づけ
a 自然死派(共同体への種々の配慮と、最後の瞬間までの生活様式の確立)
b 人工死派(自らに納得できる決断の時期の設定とその理由付け、そして共同体との
折り合いをつけるための配慮)5能動的行動
a 「さあ、来い!」という積極的に迎え撃つ心構えの構築作業
b 「さあ、行くぞ!」という心構えでの積極的行動
「自死という生き方〜覚悟して逝った哲学者」 須原一秀著 双葉社刊
この五つがそろってはじめて自死できるそうだ。すごい考察をしたものだ。ここでは「自然死」と「人工死」を区別することで、「人工死」の価値に気づかされる。
「自然死」がどういうものかをまず考える。「自然死」については『人間らしい死に方』(ヌーランド著河出文庫)という本を参考にしている。そしてこう書いている。
専門家としてのヌーランドは、「はじめに」の所で「私自身、人が死に行く過程で尊厳を感じた例に出会ったことはほとんどない」と主張し、エピローグにおいても「臨終の瞬間は概して平穏で、その前に安楽な無意識状態が訪れることも多いが、この静けさはつねに、恐ろしい代償とひきかえでなければ得られない」と言っている。
つまり、「自然死」のほとんどが悲惨なものであり恐ろしいものであるにもかかわらず、世間にはなぜか、「穏やかな自然な死」とか、「眠るような老衰死」という神話のようなものがあるが、それは間違った思い込みであることを問題にしているのである。
「自死という生き方〜覚悟して逝った哲学者」 須原一秀著 双葉社刊
つまり、恐ろしい「自然死」で死ぬか、ちょっと苦しいかもしれないが自分で選んだ「人工死」を選ぶかと、明確な選択肢を渡されてしまう。こうなってくると「人工死」もありかも、と思わざるを得ない。(もちろん思わなくてもいいんだけど)
この五段階を読んだときに思いだしたのはヒーリング・ライティングの「気持ちいいもの」のエクササイズだ。かつて、毎日ひとつずつ「気持ちいいもの」を思い出し、それを短文にまとめていた。それをし続けると(1000日間続けた)、気持ちいい感覚を以前より容易に引きよせられるようになるのだ。それと同じで、死について考え続け、体感として引きよせることで須原氏は、死ぬ状態に対しての免疫を作ったのだろう。そして、それは須原氏にとっては「免疫」ではなく、「踏み込むためのエクササイズ」だったのだろう。
この考えを自分の中に受けとると(僕の中ではまだ「さあ、来い!」とも「さあ、行くぞ!」ともとても思えないので、まだまだじたばたして生きていくのだが)、自殺しようとする人たちが、「私は自死します」と主張して死ぬような事態が生まれるのではないかと考える。そして自殺に対するある種の抵抗を「自死」と名付けることでその抵抗のハードルを低くするのではないかと心配だ。しかし、いくら僕が心配したところで、それを考えるのは個人個人の心の中なので、相談されない限りはどうしようもない。僕のような「人は自分で死んではいけないもの」という考えにしがみついている人間には「死は個人的なことで他者に束縛されるべきではない」とドライに割り切ることはできるかどうか、まだ曖昧なことにしておきたい。
この本を読んでいて「ソイレントグリーン」というSF映画を思い出した。(ウィキペディアにストーリーが書かれています) あの物語では「人がある状況に強いられていく」が、もし能動的に踏み込んでいくようになったら、いったいどうなるのだろうと考えてしまった。そして、そのことと臓器移植の類似性についても考えた。デリケートで、理解してもらうためにはかなりの文章が必要となるので、ここには書かないでおく。