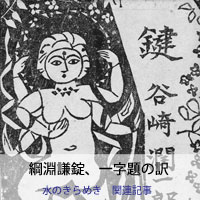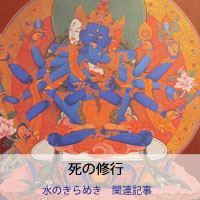村上春樹の『雑文集』を読み終えた。それぞれに面白い文で楽しく読めました。そのなかでひとつ『日本人にジャズは理解できているんだろうか』という文が心に引っかかったので、そのことについて書きます。
ことの起こりはブランフォード・マルサリスが日本にライブに来て、聴衆のあり方を見て、『日本人はジャズがわかってない』という発言をし、それについて村上春樹が論じたもの。村上春樹は表面的に起きた出来事からさらに一段高い視線を持ち込んできて、人種差別がどのように生まれるのかを感じさせてくれた。ジャズの話から人種差別の話に移行して行くつながりは、村上春樹の丁寧な説明を読まない限り正しくは理解できないと思うので、その部分をここで解説するのはやめておく。知りたい人は直接原文にあたってください。それを読んで僕の思い出したこと、感じたことを書きます。
これを読んで思い出したのは2006年のピース・キッズ・ワールドサッカー・フェスティバルのこと。八ヵ国十地域の子供たちが広島に集まり、サッカー大会をしたのです。イスラエル、バレスチナ、イギリス、アメリカ(ハワイ)、ボスニアヘルツェゴビナ、韓国、中国、沖縄、広島、川崎の子供たちが集まりました。そのときに練習のための最初の合宿所で男子トイレが異常に汚されたことがありました。大便がトイレのまわりにまき散らされていたのです。そのときは誰がやったのかわからず、ひどいことをする子がいるものだと問題になったのですが、大会のための二番目の合宿所に移ったとき、再び同じことが起こりました。一回目の状況は報告を受けただけでしたが、二回目の状況は直接自分の目で確かめました。大便用の個室の中で、便器の中はきれいなのにそのまわり、足の置き場などに大便がまき散らされていたのです。そのときにパレスチナに詳しい人が、もしかしたらとこんな話をしてくれました。「パレスチナでは水は非常に大切で、親から水は汚してはいけないと教え込まれた子がこれをしたのでは」と。
生きている場所が違えば常識が違うことは理解しているつもりでした。しかし、理解していてもそれがどのように現れてくるのか、具体的には知らなかった。本当にパレスチナの子が、水を大切にするためにそうしたのかどうかは結局はわかりませんでした。だけど日本にいただけではわかりようのないことが、いろんな出来事に影響を与えているだろうことがちょっとだけ理解できた。もしその話が本当だとしたら、そのパレスチナの子はどんな気持ちで用を足したのだろう?
『日本人にジャズは理解できているんだろうか』の最後にこう書かれています。
あるいは大げさなものの言い方になるかもしれないけれど、こういう小さななんでもなさそうな文化的摩擦を腰を据えて、感情的にではなく、ひとつひとつ細かく検証していくところから、先の方にあるもっと大きな摩擦の正体がわりに明確に見えてくるのではないか。そしてそれと同時に、日本という国家の中にあるアメリカとはまた違った差別構造の実態のようなものもひょっとして浮かび上がってくるのではないか。
ピース・キッズ・サッカーは現在ピース・フィールド・ジャパンと名称を変更し、イスラエルとパレスチナの青年たちを毎年夏に招待して合宿をしています。そこで起きることはとても些細なことばかりです。だけど、イスラエルとパレスチナの青年たちが、互いに理解するためにはきっと役に立っているのだと思う。その様を見て、日本の学生は、文化の違う人たちが互いに理解し合うこととはどんなことかに触れるのです。それに触れることで、日本という国の固有性を意識する学生もいるでしょう。
アフリカの難民キャンプで、集まってきた様々な部族が互いに理解し合うためにやったことのひとつとして、結婚式ではどんなことをするのかを話し合ったことがあるそうです。すると部族ごとにすることがあまりにも違うので、そのあと互いのコミュニケーションが楽になったそうです。違いすぎるので、とにかく話さないと何もわからないということがわかったから。
日本とアメリカなんて、互いによく理解していると思い込んでいるかもしれないけど、アメリカの地域によっての違いや、人種によっての違いなど、理解できてない些細なことがたくさんあるのだと思う。そして同じような食い違いが、本当は日本人同士にもある。
(実は、ここまでの文章は今年の二月に書いたものだった。それをPCに保存してBlogにアップするのを忘れていた。それをたまたま見つけた。アップしようとして、以下を付け加える)
僕は生まれてこのかたずっと東京で暮らしているから、田舎の生活がまったくわからない。村々でおこなわれるお祭りが素敵だなと思うけど、実際にそこにいる人がどんな思いでそれを継続しているのか、じっくりと聞かない限り理解できないんだろうなと思っている。
大震災ののち、原発はそれでも必要だと言う人がなぜそのように言うのか、僕にはちっともわからない。電力が不足したら困るだろうというのはわからないでもないが、そのために放射能汚染にさらされる可能性を抱えるのはもうごめんだ。その危険性を地方に押し付けるのもやめてほしいし、その危険性をお金で交換するというのもきわめて不快な行動だ。なぜそれほどに電力にこだわらなければならないのか、それを推進派の人たちに直接聞いてみたい。きっと十数年後、日本のがんの罹患率は上がるのだろう。でも、原発事故と罹患率上昇の関連性を示す証拠がないということで、うやむやにされるのではないかと心配だし、もしうやむやにされなかったとしても、害された健康はもう戻らない。
問題が生まれることで、それまで理解できていなかったことが理解できる可能性が生まれる。それが限りなく続く。