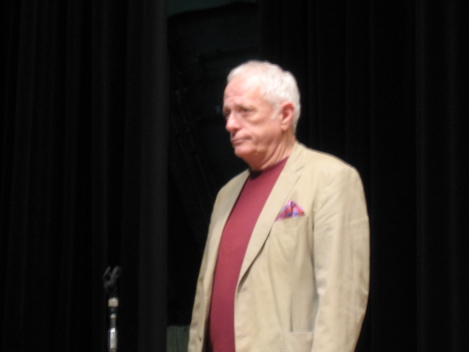今朝、茂木健一郎さんがこんなことをつぶやいた。
るる(1)そろそろ、この国をどう変えるか、本気で議論するべき時がきた。一番のポイントの一つは「ルール」だと思う。ルールを守るではなく、ルールをつくる。人と人が出会い、競う時のルール作りのセンスを、私たちは育まなければならない。
るる(2)コンピュータ・ゲームは別に脳に悪くない。ただ、ルールが決まっていて、それに従う点が創造的ではない。もっとも、自分でコンピュータ・ゲームを作るようになると、一気に創造的になる。ゲーム好きには、そこまで行ってほしい。
るる(3)子どもたちは、楽しく遊べるためのルールを作る素晴らしい能力を持っていている。たとえば、「みそっかす」。弱い子、幼い子は、特別扱いして少し有利にしてあげる。そうすることで、誰が勝つかわからなくなり、ゲームの楽しさが増すのだ。
るる(4)草野球をやっていて、弱い子が来ると下手投げにしてあげる。三振なしにする。送球も、ちょっと手加減する。子どもがそうするのは、弱者保護の麗しい理想からではなくて、そうやることでゲームとして楽しくなるのだ。
るる(5)ババ抜きで、幼い子がババを引くと泣き出すから、わざとそのカードを少し上に出したりする。幼い子も意味がわかるから、それを避けてセーフになる。こういう「みそっかす」も、楽しく遊ぶための智恵だ。
るる(6)ルールをつくる上では、多様なバックラウンドを持った人が、みな勝ったり負けたり、いろいろあるようにした方が楽しい。いつも誰が勝つか決まっていたり、負け続ける人が出るようなルールは、ゲームをつまらなくする。
るる(7)「新卒一括採用」は、ゲームのルールとして全くつまらない。マジメに黙々と従った人だけが有利となり、途中でふらふらしたり、飛び出して戻ってきた人は負けると決まっている。そんなゲームは、誰の胸もわくわくさせない。盛り上がらない。
るる(8)ペーパーテスト一辺倒の大学入試も、全くつまらない。ハーバード大学だったら、市川海老蔵や卓球の愛ちゃんもそのまま受かるかもしれない。東京大学は小難しい試験を解けないとダメだ。どちらが「ルール」として面白いか、歴然としている。
るる(9)日本人は従順だから、誰かが決めたルールに黙々と従って、その中で上位に来た人を「エリート」と呼ぶ。つまらない。本当のエリートは、みんなが楽しく遊べるように、ルールを工夫する人のことを言う。子どもの時、夢中になって遊んだ頃のことを思い出してごらん。
これを読んでいいこと書くなと思った。そして思い出したのは、9年前に中学校でした講演だ。ここにまとめがある。
ポイントは「誰でも誰かの役に立ち、誰かの世話になっている」ということ。講演会で僕は肉食獣の話から比喩を作った。
肉食獣は我が物顔で草食獣を食べるが、視点を変えると、彼らは草食獣がいてくれるおかげで生きていられると言えるし、もっと言えば、広い草原があるから生きていられるとも言える。僕は今朝、目覚まし時計で起きた。朝食を食べ、電車に乗って目白駅まで来て、千登世橋中学校に到着した。僕は目覚まし時計を使うし、朝食は僕の意思で食べた。電車もお金を払って乗った。我が物顔でそれらを使ったり食べたりしているが、視点を変えると、それらを作ったり、運行してくれる人たちがいなければ時間通りにここに来られなかっただろう。
社会は僕たちにとっての生態系だ。多くの人が活き活きと生きてないと、その生態系はうまく機能しなくなる。僕たちは、古いマーケティング的な考え方に侵されたため、大切な考え方を見失ってしまったのではないか?
僕たちは社会のパラダイムを変える、その変節点にいる。いま変えずにいつ変えるのだろう。市場は消費者の搾取から生まれるのではない。かつて消費者と名付けられた人は、生産者であり、役人であり、政治家であり、農業従事者であり、漁業従事者であり、工業労働者であり、弁護士であり、ありとあらゆる職業の人の総体なのだ。消費者を豊かにすることこそが市場を作る人の仕事だ。その観点を忘れ、従事者から搾取し、消費者から搾取し、ありとあらゆる人を出し抜くことで市場を作ろうとするのは正しくないこと。一方で、消費者からの観点も変化しなければならない。物を買うとき「安い方がいい」という価値観だけで物を買う限り、市場から搾取していることにほかならない。適正な価格とは何かを消費者が考えない限り、市場は育たない。飲食業では安い食べ物を提供しようと、安全性には目をつぶることがよくあるようだ。それは、消費者がそのようなものを求めるからそうなってしまう。物を買うとき、正しい価格で買う知恵を持つことが、すべての人に求められるようになっていく。その知恵を持たない人は「衆愚」と言われても仕方ないだろう。かつて江戸に住んでいた人たちは「宵越しの銭は持たない」ことを信条にしていたという。なぜか。江戸は火事がよく起きた。もし銭を抱える生き方をしていたら江戸はまったく潤わず、町には活気が生まれなかっただろう。自分が持っている銭は誰かに与えることではじめて生きる。その考え方がきちんと生きていたのだ。
僕たちは権利ばかり言いつのり、自らが学ぶことを忘れているのかもしれない。便利な物ばかり求めるが故に、じっくりと考えることを忘れているのかも。