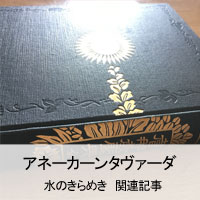ドキュメンタリー映画「The Cove」のDVDが手に入ったので、友人知人10名ほどで一緒に見ました。
見終わったあとでそれぞれの感想や意見を交換し合ったのですが、それがとても楽しかった。いろんな思いが噴出します。ある人は「動物を人間が簡単に殺してしまうことが問題だ」といい、ある人は「ここで言われている水銀とは、どんな水銀かはっきりしないのでもっと詳しく説明しなければ駄目だ」といい、ある人は「意見が偏りすぎている」といい、そしてある人は「殺されたイルカが最後に尻尾を振っているのが痛ましかった」と言いました。そして、全員一致したのは「もっとたくさんの日本人がこの映画を見て、その上で言いたいことをいい、変えるべきところを変えればいい」ということでした。
この映画を見れば、主人公であるリチャード・オバリーがどんな悲しみを抱えているのかがよくわかります。彼に共感する人はきっとイルカ殺しをやめようと声を上げ始めるでしょう。それが怖くて漁業関係者はこの映画を日本で上映させたくないのかもしれません。
仕立てはイルカ殺しをやめさせようとする映画ですが、深いところに横たわる問題はコミュニケーションの断絶です。
太地町の漁民たちは明らかに被害者です。一方で加害者でもある。リチャード・オバリーやこの映画の制作者も被害者であり、加害者です。互いに被害者であることばかりを訴えても話は先に進みません。同様に日本人も被害者であり、加害者です。この問題を無視し続ける限りそれは変わりません。この映画は日本以外ではかなりの注目を浴びています。それがなぜなのか、いまの日本人には理解できません。なにしろその作品すら見られないのですから。2010年1月30日現在で44もの映画賞を受賞しています。そして、オスカーの候補作としても残っています。
この映画が日本で見られないのは、他の国とのコミュニケーションの断絶を深くするだけです。見たあとで他の国の人たちといろんなことを言い合えば良いのです。それができないことが大きな問題です。この映画は見た人がみんな何か言いたくなるような面白さがあります。つまらないから上映されないのではないでしょう。
イルカ保護の団体がこの映画の無料自主上映会をします。その際にパネルディスカッションがあり、パネラーとして呼んでもらいました。僕は必ずしもイルカ保護を訴える者ではないので、どんな話になるか楽しみです。
イルカから地球環境を考える「海・イルカ・人」Vol.3
2010年度 アカデミー賞 長編ドキュメンタリー部門 ノミネート作品
「THE COVE」(ザ・コーヴ )上映 & トークセッション
日 時: 2010年2月11日 (木・祝日)
時 間: 14:30〜21:30(4部構成)
* 部分参加可。詳細は下記をご参照ください。
参加費:無 料(但し事前予約が必要です)
会 場: 国立オリンピック記念青少年総合センター「センター棟 101号室」
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1
アクセス:小田急線 参宮橋下車 徒歩7分、
(駅にアクセス案内有り)/ 地下鉄千代田線 代々木公園駅(C02)下車、
(代々木公園方面4番出口)徒歩約10分 / 京王バス 新宿駅西口(16番)、
渋谷駅西口(14番)より代々木5丁目下車 すぐ。地下駐車場有ります。
詳細サイト⇒ http://nyc.niye.go.jp/facilities/d7.html
会場内での食事は禁止です(飲み物OK)/
2階にカフェ、近隣の棟にレストラン、売店が有ります
主 催: エルザ自然保護の会
〒305-8691 茨城県つくば市筑波学園郵便局私書箱2号
http://www.elsaenc.net/index.htm
協 力: オフィスタラーク、DRUMAGIK、パンゲアシード、サークリット
ご予約方法: 「サークリット」まで、メール、お電話、FAXでご予約下さい。
E-mail circlet@gem.hi-ho.ne.jp
TEL 0422-22-0311 FAX 0422-22-0312
※ なるべくメールでお願いします。
ご予約の際は、1.お名前、 2.Eメールアドレス、3.お電話番号、4.4部のうちの
どの部に参加ご希望かをお知らせ下さい。
ご希望の部を自由に 組み合わせて、あるいは、一部のみのご参加も大歓迎です。
E-mailでご予約の際は、件名を「2月11日イベント参加希望」とご記入下さい。◆映画とイベントの内容◆
<第1部・第4部>海外各国で大きな話題となっている
日本のイルカ猟を題材にしたドキュメンタリー映画「THE COVE」を
上映します。
今回、この映画の監督であり、OPS代表のルイ・サフォイアス氏と、
映画の中心人物であると同時に、イルカの保護・救済活動を世界的に続けている
SJD代表のリチャード・オバリー氏の希望によって、
この映画が資料映像として上映されることになりました。
イルカが好きな人、環境汚染や食の安全について考えている人はもちろんのこと、
あらゆる世代の人々に観ていただきたい作品です。
<第2部>重金属問題のスペシャリストで
財団法人政治経済研究所環境問題研究室主任研究員の小野塚春吉先生の講演と
質疑応答。演題は「高次捕食性海生生物における環境汚染物質の
濃度レベル—健康影響の視点からの考察」
<第3部>小野塚春吉先生、ライターとして活躍されている
オフィスタラーク主宰のつなぶちようじ氏、
及び作家でエルザ自然保護の会事務局の辺見 栄が加わり、
水銀問題をはじめ、イルカ猟から水族館の話題まで、
多岐にわたってお話します。
司会進行はイルカの取材を長年続けている映像作家の坂野正人が担当します。
どなたでも気楽にご参加頂き、みなさんの意見交換の場になれば…と思います。
まず、真実を知ることからはじめてみませんか?◆プログラム◆ *時間は多少遅れる場合がございます。ご了承ください。
14:10〜 受付開始 *受付でお名前をご確認してからお入りください。
自由席となっております。
第1部 14:30〜16:00 「 THE COVE 」 1回目上映
第2部 16:20〜17:10 小野塚春吉先生のお話とQ&A
テーマ「水銀汚染と健康への影響およびその対策」
第3部 17:30〜19:30 パネルディスカッション
メインテーマ「イルカから地球環境を考えよう」
第4部 20:00〜21:30 「 THE COVE 」2回目上映
*お話の会に参加できない方のご参加も大歓迎です。