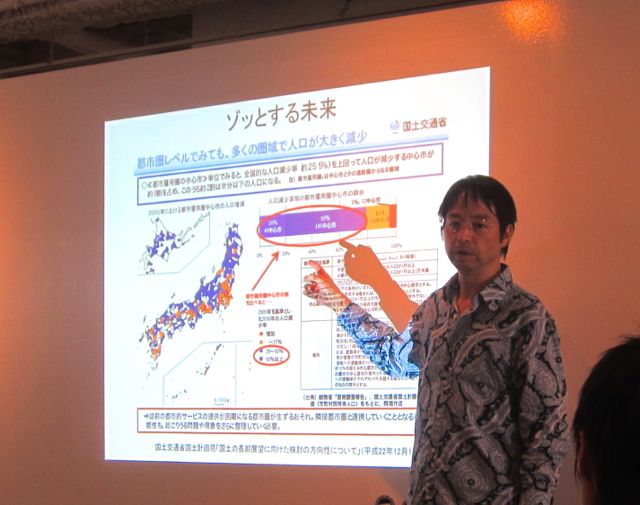「しちだ」グループの右脳開発友の会が発行している『右脳開発』に三回にわたり原稿を掲載しました。こちらにその文章を転載いたします。
第一回 地球の進化について語った神父 2013年7月号掲載
『胎内記憶』を故七田眞先生の共著者として98年7月にダイヤモンド社から出版させていただきました。その際に七田先生に何度かお目にかかりお話しをうかがいました。
そのときの印象は一言ではとても言い表せないものですが、あえて言うなら聖人のようなかただなと思いました。たいていのことは「そうですね」と受け止めて下さいますが、少しでも意見が違うと「僕はこう思うんです」と言って、そのあと丁寧に話をして下さいました。その話は理解を促し、共感をも生み出すような話し方でした。そして最後に「違いますか?」と確認を求められる。自分の内側で固まっている常識やパラダイムを少しずつ解かしてもらうのは、このような話し方なのだろうと思いました。七田先生は、それまで強固にあった教育に関しての常識や思い込みを、年月をかけて新たなものにしようとし、実践してきたかたなのですから、当然と言えば当然なのかもしれませんが、話をうかがいながら何度も頭の下がる思いがしたものでした。
世界には七田先生と同様に、常識をくつがえした偉人が何人もいますが、この10年ほど僕が研究しているのはピエール・テイヤール・ド・シャルダン(1881〜1955)という人です。『現象としての人間』という本を書いたことで有名ですが、神父でありながら地層学者であり、古生物学者でもありました。テイヤールはカトリック神父のため、大きな矛盾にさいなまれます。自身は進化論を信じているが、神父という立場がそのことについての発言を邪魔します。凡庸な人物であればここであきらめ、神父をやめるか、科学者をやめるかしたでしょう。しかし、テイヤールは相いれないふたつの立場を保持しながら、それぞれの思想を深めていきます。そして、身の回りに生じる逆境を、次々と好機へと転換していくのです。
たとえば、ヨーロッパで彼の発言が問題になったとき、カトリックは根回しをしてテイヤールを北京に送ったようです。北京に行けば人の噂も静まるだろうと考えたのでしょう。ところがそこでテイヤールは次々と古生物学や地層学についての発見をし、ついには北京原人の頭骨の発見にまで関わります。その結果シトロエンがスポンサーとなり、車での中国大陸横断を果たし、それが映像にもなり、広い層の人たちに知られるようになってしまいます。このような状態になるとカトリックの神父といえども、進化について公で何度も話をする機会に恵まれます。当然その内容を出版することを望まれるのですが、カトリックが許してくれません。
シャルダンの著作は生前出版されることがなかったのですが、死後、彼の思想を大切に思った有志が集まり、テイヤール遺稿刊行委員会を結成し、そこが次々と出版し、欧米諸国ではベルクソンやアインシュタインと並び称されるほどの驚きをもってこの著作集は受け入れられました。
テイヤールがどのように当時の人々の常識をくつがえしていったのか、そして、そのことがどう右脳開発と関係があるのか、あと二回の原稿に簡単ではありますが書かせていただきます。