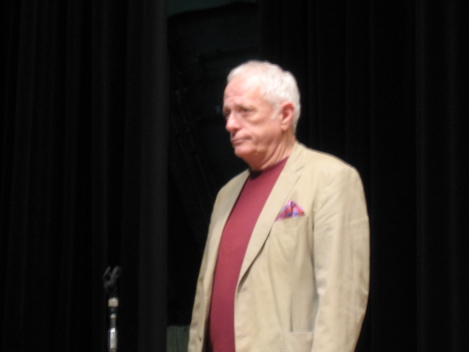PCの技術が発展して以来、あらゆるメディアが溶解・統合して、まるで『ブラッド・ミュージック』に登場するナノマシンのようになってきている。普通のナノマシンはただ小さいだけだが、『ブラッド・ミュージック』に登場するナノマシンは知性を持って生物と融合し、ハイブリッドな生命としてバージョンアップしていく。
現在は『ブラッド・ミュージック』のように簡単にハイブリッドされる訳ではないが、PCの技術はいたるところに応用され、アナログだったレコードをCDとし、デジタル化された信号を取り込むことを覚え、ついにはiPodのような小さな機械に何千、何万という楽曲を詰め込むことができるようになった。
かつては音楽が聴けてビデオが見られる機械となると、ふたつの機能を持たせるために大きくなったものだが、いまでは両機能がiPod nanoの大きさに収まってしまう。20年前の人間が見たらどんなに驚いたことか。
と同時にどんな機械も、その大きさは自由になっていく。かつては大きさに制限があった。それをどんどん小さくすることができるようになり、今度はかつてとは反対に、使いやすくするために大きくすることを考え始めている。大きくすると、余ったスペースをどう利用するかで競争が始まる。このとき必然的に機能のハイブリッド化が始まる。
バーチャルな空間はいくらでも広げられる。その感覚を現実に持ち込む人がいつか現れるだろうが、その感覚がどのようなものか、かつてのパラダイムにいる僕には想像もつかない。たとえば、宇宙空間での無重力状態の映像を当たり前のように見る人たちは、きっと新しい空間認識を始めるだろう。それと同じように、機械に必要だった空間をいくらでも大きくしたり、小さくしたりできる感覚を持つと、僕のような古い人間には考えつかないような突飛な機械を作り、いままでは考えられなかった機械の使い方を始めるのだろう。機械をからだに埋め込むなんてのはまだ序の口で、もっと不思議なことが始まると思う。
たとえば、コードのないイヤホンだけの電話とか、家の壁がその日の気分によって好きな写真や絵画で埋め尽くされるとか。広大な土地にモニターを敷き詰め、Google Earthに毎日のように美術作品を見せるようにするとか。でも、それでもまだまだ古い人間が考えるようなことだ。そうだ、地球全体で電波望遠鏡も作れるだろう。携帯電話に特定方向から来る微細な電磁波を受けとる仕組みを入れて、位置情報、アンテナ方向と統合することで地球の大きさの電波望遠鏡ができあがる。
政治も次々と情報が開示され、多くの人がアイデアを提供して、たくさんの人にとっていいと思われる工夫が積み重ねられるようになるだろう。いままで特定の人が抱えていた権利はオープンにされ、使いたい人がいつでも使える状態になっていく。自転車や車がバイクシェア、カーシェアされるように、権利や義務も特定の人に属さず、シェアされるようになるのではないか? これはまだしばらく時間がかかるかもしれないけど。
これからの時代はいままでのどの時代にも増して、人間のイマジネーションをどこまで拡大できるかが問題になる。その加速度がさらに大きくなってきた。